分離とは
アルファ・ラバルの創業者グスタフ・デ・ラバルが19世紀に世界で始めて遠心分離機を実用化して以来、140年以上にわたって様々な産業において分離技術でプロセスのイノベーションを進めてきました。当社には、分離技術だけでなくプロセスノウハウを持った専門家がおり、世界中のお客様に対して「高効率・高信頼性・低コスト」を実現する分離ソリューションを提供することでビジネスの成長に貢献しています。このページでは、分離機に関する様々な情報を発信しています。
分離技術の種類
様々な産業における液体の分離に用いられる技術は多岐に渡りますが、ここではアルファ・ラバルが提供できる液体製品の分離技術を(1)図で紹介しています。縦軸が対象液中の固形分含有量(v/v%)、横軸が処理可能な粒子径です。
アルファ・ラバルの分離技術(1)
デカンター型遠心分離機
デカンター型遠心分離機は10µmから1㎝までの固形分を入口固形分量で最大60%まで処理できます。対象液をビーカーに入れて12時間放置して上清が透明になればデカンタ型を適用できます。最も採算に合うのは30分放置して上層が1㎝でも透明になるサンプルです。
ディスク型遠心分離機
ディスク型遠心分離機 は0.1µmから1㎜までの固形分を入口固形分量で最大25%まで処理できます。対象液をビーカーに入れて12時間放置しても上清が透明にならないサンプルがディスク型に向いています。最も採算に合うのは1µmから10µmが主体に含有する液です。また、比重差が1%までの液液分離に最適なのがディスク型です。
ディスク型には大きく3つのタイプがあり、固形分含有量で使い分けています。対象液の固形分含有量は、試験管遠心器を使って、弊社経験から遠心力×遠心時間(分)が12,000の条件で振って、その沈殿のパーセンテージです。固形分がゼロか1%未満の場合、固形分保持型(2)、固形分がゼロから10%以下の場合、間欠排出型(3)、固形分が10%以上25%未満の場合、連続排出型(ノズル型)(4)を適用します。
固形分保持型(2)
間欠排出型(3)
連続排出型(ノズル型)(4)
メンブレンフィルター
メンブレンフィルター は0.1µm未満の固形分除去や比重差のない物質間の分離や濃縮に適用します。
分離機の用途
ディスク型遠心分離機は、液液分離と固液分離を含む産業用の分離プロセスに使用されます。
- 液液分離は、密度の異なる2つの非混和性液体に適用されます。
- 固液分離は以下に適用されます:
-懸濁液から貴重な固形分を回収し、廃棄物として液体を排出処理する
-懸濁液から貴重な液体を回収し、廃棄物として固形物を排出処理する
-固形物と液体の両方を貴重な製品として回収する
-または環境への汚染を防ぐために、液体から固形物を取り除いてから液体を洗浄する - 液液固分離には、3つの非混和相の分離に適用され、最も困難な分離プロセスとなります。ここでは、ディスク型遠心分離機が圧倒的な強みを発揮し、他の分離技術は競争できません
6つの分離形態
ディスク型遠心分離機を適用できる6つの分離形態を紹介します。
清澄
液中から懸濁固形分を除去します。分離機のタイプとしては、間欠排出型または連続排出型を適用します。
清浄
互いに混じり合わない2液を分離します。固形分を同時に分離する場合もあります。固形分を含む場合は間欠排出型、固形分を含まない場合は固形分保持型の分離機を適用します。
脱水
スラリーから液体を除去して濃縮します。間欠排出型または連続排出型を適用します。
分級
含まれる固形分をサイズによって分けます。粒径が小さいものを上清液、大きいものを固形分として分離します。間欠排出型または連続排出型を適用します。
洗浄
洗浄水の添加により固形分に同伴する不純物を洗浄水側に移動させます。主に連続排出型を適用しています。
抽出
溶剤添加により、欲しい成分を溶剤側に移行させます。主に固形分保持型を適用しています。
ディスク型遠心分離機の原理
世の中には様々なタイプの分離技術が存在しています。その中でも遠心分離機は、遠心力を利用して液体中に含まれる比重(密度)の異なる物質を分離する装置です。その最大のメリットは遠心力だけで処理液中に分散した固体や液体を効率よく的確に分離できることです。
工業用遠心分離機は、大きく「遠心沈降機」「デカンター」「遠心脱水機」に分類することができ、ディスク型遠心分離機は「遠心沈降機」の一部になります。
遠心力で固体・液体を分離
ディスク型遠心分離機は、回転軸の回りに下に開いた円錐形(傘型)のディスク(分離板)を積み重ねることにより、9m2という据付面積で300,000m2以上の広大な分離沈降面積が達成できる構造となっています。これにより、小さなスペースで大量・高速の分離が可能です。ディスクは0.5mmの間隔で数百枚積み重なり、ディスクの間に5,000~15,000Gの遠心力がかかって分離は瞬時に終了。粒径0.1ミクロン、比重差2%までの固液、液液分離を連続的に行えるため、お客様のプロセスにおける“大量処理” “コストパフォーマンス”“信頼性” の3つのニーズに応えることができます。
遠心分離機は処理液中の重い物質の重力による自然沈降を、遠心力によって時には重力の10,000倍を超える力に変換して沈降分離を促進させる仕組みです。処理液中に浮遊する固体粒子が落下する際の重力沈降速度Vgはストークスの法則で表せます。
この式から分離する2物質の比重差や固形分の粒径が大きく、処理液の粘度が小さいほど、より早く分離することが分かります。液中の物質を沈降法で効率よく分離するには、
❶粒子の重力沈降速度Vgを上げ、❷粒子の分離面までの沈降距離を短くする、の二つの方法が考えられます。
❶のためには、ストークスの法則の重力加速度gを遠心力に置換えることで沈降速度を上げる。
❷のためには、底面積を広くすることで分離面までの沈降距離を短くする。
この二つの原理がもとになりディスク型遠心分離機のアイデアへと発展しました。
先ほどの沈降距離を短くするために容器の中に板を入れると、底面積の広い容器を使わなくても沈降距離を短くできます。
さらに、薄い板を何枚も重ねるように傾斜させて挿入することにより大量分離、連続フローに対応でき、より早く大量に沈降・分離します。そして遠心力を使うために円筒形の容器の中に薄い板の代わりに傾斜の付いた円錐状ディスクを挿入し、処理液の入口・出口を設けて「ディスク型遠心分離機」のボウルが完成しました。固液分離の場合、ボウルの中に供給された処理液はディスク間で瞬時に固形分と液体に分離されます。固形分はディスク間上部を遠心力方向に移動し、液体はディスク間下部を通って中央に分配されます。ディスク型遠心分離機処理量Qは理論的に次の式で表されます。
ここでΣはディスクの物理的形状と回転速度を組合わせた分離沈降面積と呼ばれるもので、
と表されます。すなわち、ディスク型遠心分離機の性能は分離沈降面積Σによって決まります。一般に円筒(シャープレス)型遠心分離機は回転による遠心力だけでΣを上げていますが、処理能力アップの条件は遠心力だけではなく、Σの式でも分かるようにディスクの枚数、大きさ、角度なども大いに関わっています。この要素に着目して処理能力を飛躍的に高めたのがディスク型遠心分離機というわけです。ディスクの採用により分離沈降面積Σが遙かに大きく取れるようになりました。
ディスク型遠心分離機のメリット
- 固液、液液、液液固分離ができます。
- 遠心力は最大15,000Gで、0.1ミクロンまでの粒子がフィルター助剤や凝集剤なしに分離できます。
- 滞留量が小さいので処理液の切替や処理停止がすばやくできます。
- オートメーション化がきわめて簡単で、人件費が節約できます。
- 空気に触れてはいけない場合、密閉運転ができます。
- 分離を瞬時におこない、処理液の変性などを抑えることができます。
- 完全連続運転で、長時間の無人運転が可能です。
- 防爆仕様が可能です。
- 据付スペースが極めて小さくて済みます。
ディスク型遠心分離機の構造
ディスク型遠心分離機の心臓部はボウルと呼ばれる回転体で主要パーツはボウルボディ、ディスク、ボウルフードです。モータの回転をギアで増速させ、スピンドルを介してボウルは数千回転で駆動します。フレームフードでボウルは覆われており、様々な入口、出口機構を提供しています。間欠排出型では排出時の風圧を抑制するサイクロンを介して固形分が排出されます。
処理液入口(インレット)の種類
オープン
回転しているボウル内に固定のパイプから処理液が供給されます。製品は空気と接します。
セミヘルメチック
オープンタイプにディスクインレットというパーツを挿入して半密閉状態を作れます。
ヘルメチック
メカニカルシールを介して処理液はスピンドルの中空部分からボウルに供給されます。インレットで製品は一切空気と触れません。
処理液排出口(アウトレット)の種類
オープン
空気中に噴き出し、自然落下します。
ペアリングディスク
液出口部分に固定のインペラーが装備されており、液の回転エネルギーを吐出圧力に換えて、液を圧送できます。出口に背圧をかけることで液中の空気をゼロにすることができます。
ヘルメチック
出口にメカニカルシールを装備して空気混入なしに液中で回転するポンプで圧送されます。
固形分排出口の種類
オープン
間欠排出型、連続排出型ともに固形分はボウル外周部からフレームケーシングで囲われている空間に噴き出されます。
ペアリングディスク
安息角が20°未満の固形分しか適用できませんが、固形分はボウル中心部に装着されたノズルから連続排出され、固定のチューブで吸われて圧送されます。
業界別の事例
アルファ・ラバルは様々な業界の分離課題の解決に貢献してきました。そのいくつかをご紹介します。
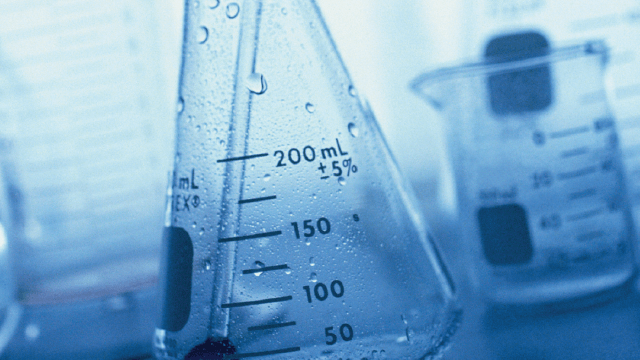
ディスク型遠心分離機のラインナップ
分離機と言っても、お客様が求める分離の目的や条件は様々です。アルファ・ラバルは、業界・用途ごとに最適化した製品ラインナップを用意しています。

アルファ・ラバルが選ばれる理由
アルファ・ラバルは140年にわたって様々な業界のお客様の分離課題の解決のお手伝いをしてきました。それは海外はもちろん、日本においても同様です。日本のお客様がアルファ・ラバルを選ぶ理由は、単に分離機の性能が優れているからだけではありません。こちらではその4つの理由をご紹介します。

アルファ・ラバル独自のディスク型遠心分離機の最新機能
すべてのアルファ・ラバルの分離機は、140年以上の経験とプロセスノウハウの蓄積を活用して開発されています。その専門知識のすべてが、どのように分離機を進化させる最新の機能・構造として組み込まれているかご紹介します。

世界で初めて市場へ導入したバイオ製薬 細胞分離回収プロセス向け シングルユ—ス仕様 ディスク型遠心分離機
UniDisc:最新型 溶接レス構造の分離板で分離効率と洗浄性を革新
eMotion:消費電力を最大 70% 削減する独自のシステム
分離機で省エネと水使用量を削減
ビール醸造業界に向けて、その電力と水の使用量の多さからサステナビリティへの取り組みを求める声が高まっています。アルファ・ラバルのサステナビリティ・アグリーメントは、省エネ化・水使用量の削減を実現できるオプション機器を初期投資不要のサブスクリプション形式で提供するサービスです。これにより分離機が環境に与える影響を低減することができます。

